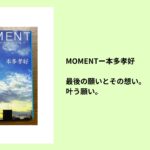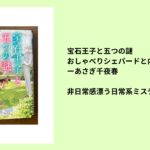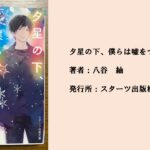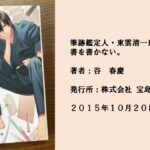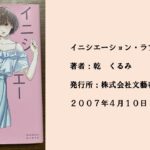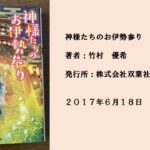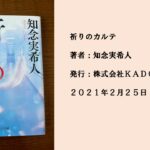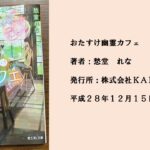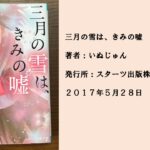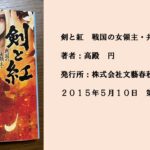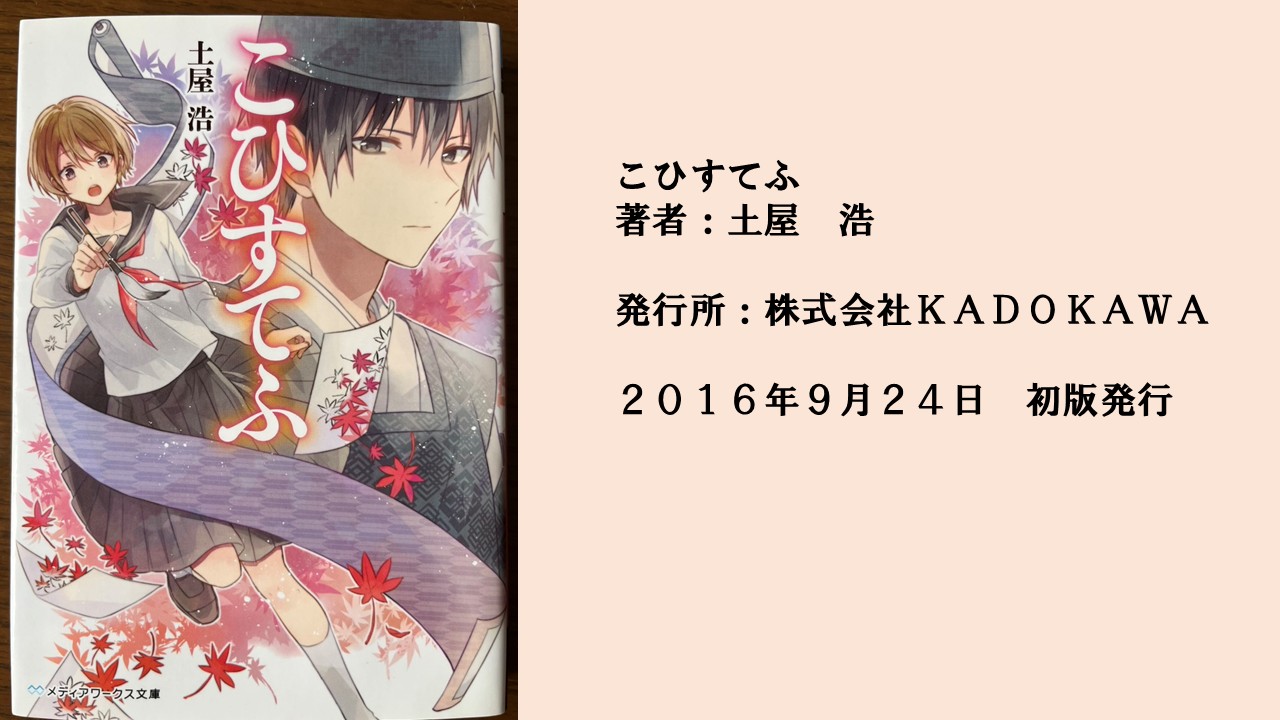
※一部あらすじよりも踏み込んだネタバレがありますので、お気を付けください。
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
こんにちは!百人一首が今さら読んでみたくなっているYUKIです。
今回は土屋浩先生の「こひすてふ」をご紹介していきたいと思います。
今作は女子高校生の「御厨紀伊」が平安時代にタイムスリップし、和歌を愛する三十六歌仙の「壬生忠見」と出会う物語です。
「紀伊」は幼少期に神童と言われたほど絵が上手な女の子だったのですが次第にその自信を失い、学校の美術部で自信なく絵を描いている女の子です。
その「紀伊」が平安時代にタイムスリップし、壬生忠見と出会い、和歌に合わせて絵を描くことで次第に、才覚を取り戻していきます。
「互いに影響を受けあう芸術の物語が読みたい」
「伏線がある複雑な物語が読みたい」
「過去の作品に思いを馳せる気持ちや余韻を楽しみたい」
そんな方にはおすすめの一冊です。
今作は「紀伊」という画家が「壬生忠見」という歌人が、日々の行動や言動、考え、そして創り出す作品によって影響を受けあい、心を動かされる作品を生み出していくシーンが多くあります。
また、単なる読みやすい作品ではなく、伏線があらゆるところに巡り張らされていて、読み進めながら「ああ、だからこうつながるんだ!」と驚くことが何度もありました。
そして、平安時代という舞台にしているからこそ、史実にゆとりがあり、その余韻を楽しむことができます。
今作を以下の3点にまとめて魅力をご紹介していきたいと思います。
- 自分の内面にあるものを外側の影響から引き出す
- 足元を掬われたような感覚になる伏線回収
- 和歌とともに歴史を味わう物語
主人公「御厨紀伊」は自分の絵に自信がないところからスタートします。しかし、「壬生忠見」と出会い、会話をし行動していくことで関係性が生まれていき、ついには他の画家が驚くような絵を描き上げるまでになります。
また、物語全体を通して、自然に伏線が張られていき、突然回収されるので、足元を掬われたような感覚になります。その感覚がとてもクセになります。
そして、平安時代という舞台と和歌という考える余地を楽しむ芸術が相まって、「これはこう考えたからこういったのかな」とか「史実が変わることってあるけれど、こんなことがあったからなのかな」と作品を味わうことができます。
以下それぞれのポイントについて深堀していますので、気になった方はこの記事を読んでみてください。
自分の内面にあるものを外側の影響から引き出す
今作の主人公「御厨紀伊」は幼少期に神童と言われ、自分自信も調子に乗ってしまい、そのことを後悔しながら、自信なく絵を描き続けている高校生です。
彼女は自分に自信がなくなったことで、周りへの評価が気になり卑屈になっています。
しかし、平安時代にタイムスリップし、歌人「壬生忠見」と出会うことで、絵を描くことに熱中していきます。
その絵は他の絵師が驚くほどの絵へとなっていきます。
それは「壬生忠見」に絵の才能がありアドバイスしたからではなく、彼が彼女自身の内面にある才能を引き出したからであり、だからこそ彼女はある決断をすることになるのです。
足元を掬われたような感覚になる伏線回収
この作品は本当に自然に伏線を張ります。しかもその伏線がとてもきれいで何重にもなっています。
気づいたときには足元を掬われて、読者はすっころんでいるのですが、「悔しい」というきもちより、「やられた」と思う清々しさがあります。
「そんなところが伏線回収されるの?!」
「そこは回収したはずじゃ・・・!?」
という感覚に私はなりました。
あまり話過ぎると楽しめなくなってしまうので、詳細はぜひ読んで確かめてみてほしいです。
和歌とともに歴史を味わう物語
今作の舞台は平安時代です。そしてテーマは「和歌」。どちらも不確定な要素が残る題材です。だからこそその余白を私たちは想像し、楽しむことができます。
そして主人公「御厨紀伊」はその余白に筆をとり描いていく、という物語になっており、作品として、その意味は一つ一つ描いていきます。
加えて平安時代を舞台にしているからこそ、現代の史実に違和感を覚えることなく、ストーリーが展開されます。
ラストの方は「歴史に対して、そんな考え方のアプローチがあるんだ」と感動しました。
まとめ
今回は土屋浩先生の「こひすてふ」をご紹介していきたいと思いました。
内面にあるものを、他人を通して生み出す不安定さ。だからこそ生まれたものに意味が見いだせるのかもしれません。
物語全体を通して丁寧に組み上げられたストーリー展開。
そして「平安時代」という舞台、「和歌」という余白を味わうテーマによって、読者のこちらも読んでいて楽しくなる作品だと思います。
ぜひ気になった方は、読んでみてください。
後半は伏線回収されるたびに、驚きと納得の連続です。
それでは良い読書ライフを!