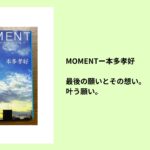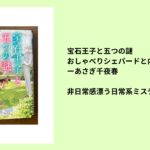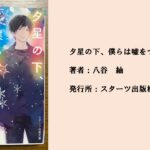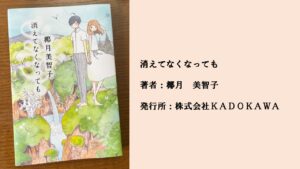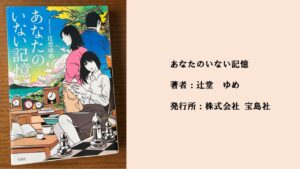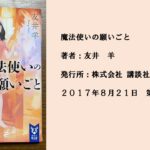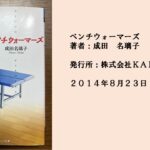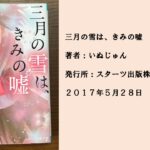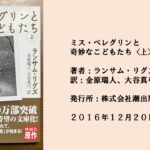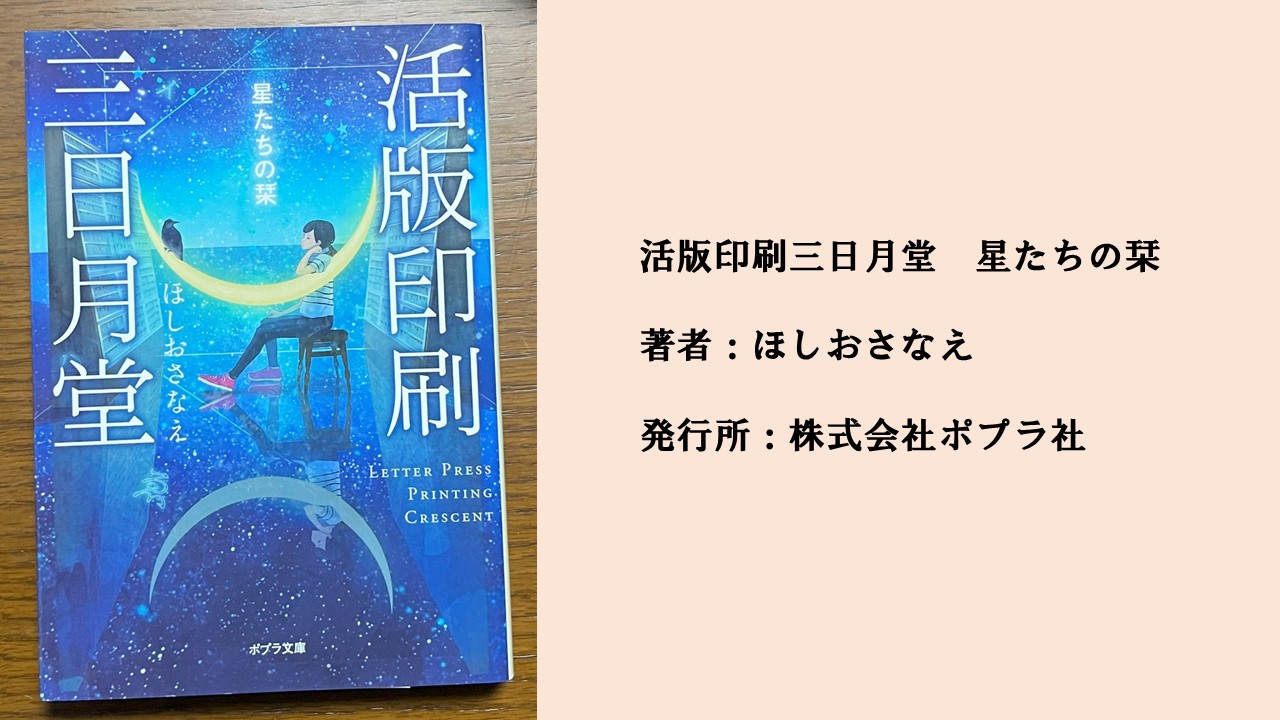
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。
こんにちは!活版印刷の文字に触れてみたいYUKIです。
今回はほしおさなえ先生の「活版印刷三日月堂 星たちの栞」をご紹介いたします。
あらすじ
現代の印刷方法とは異なり、人が一つ一つ選んで印字する活版印刷。
川越の神社の向かいに古くからある活版印刷を営む「三日月堂」に新たな店主が現れる。
訪れるお客さんたちはさまざまな悩みを持ち、「三日月堂」の店主「弓子」は彼らの悩みを自分ごとのように考え、彼らの悩みに寄り添います。
そんな弓子のアドバイスやサポートによって、彼らの悩みは解決の糸口をつかんでいきます。
こんなこと思ってたらぜひ読んでみて!
伝えたいけれど言葉にするのが難しいことがある
「活版印刷三日月堂」の主人公たちは、誰かしらに伝えたい言葉があります。
巣立っていく息子、自分が営むお店のお客さん、自分よりも優れている友人や、これからともに歩むことを決めた恋人。
主人公たちは彼らに対して、言葉をすることが難しく感じています。
そんな主人公たちに対して、「三日月堂」の店主「弓子」は活版印刷を通して、彼らの悩みに寄り添います。
そして彼らは活版印刷に相手への思いを込めて刷っていくのです。
読んでみて気づいた魅力
活字の仕事と役割
活版印刷屋の商売道具は活字で、印刷された文字を販売します。
そのため、活字がなければ活版印刷屋を営むことはできません。
しかし、お客さんに渡すのは印刷物ですので、価値があるのは浮かび上がった文字です。
これが「三日月堂」の店主である「弓子」に重なりました。
「活版印刷三日月堂 星たちの栞」では「三日月堂」の店主である「弓子」のお話しは登場せず、「三日月堂」に来店するお客さんたちのお話しばかりです。
あくまでも弓子は主人公たちが悩みを解決するきっかけを与えるに過ぎません。
しかし、弓子を介したことで伝えられた言葉があると思うと、弓子自身が活字の役割を果たしていたんじゃないでしょうか。
読了した方と語りたい話 ※ネタバレを含みます
※ここからは今作を読まれた方とこんな話をしたいなと思い書いています。
※ネタバレを含みますので、読了されてから読むことをおすすめいたします。
現代に再評価される活字
最終話「ひとつだけの活字」では曽祖父が活字屋を営んでいた「佐伯雪乃」が登場します。
雪乃は祖母が持っていた活字を今でも大切に持っており、その活字を使って結婚式の招待状を作りたいと考えていました。
しかし、現代には雪乃が持っている活字を作っていた職人どころか、活字を作る職人はいませんでした。
そこで知ったのは活字は「ただひとつ」だということ。
現代の印刷技術はどのパソコンからでも同じ字を印刷することができますが、活版印刷では同じ活字でなければ同じ文字を印刷することはできません。
それは活字職人が一つ一つ手作業で彫っていたからです。
今は品質の高いものが大量に作られる時代で、品質の高さに価値は生まれにくくなっています。
そんななかで「ただひとつ」しか作れない活字というものは、代わりがないからこそ思い出を強烈に残してくれる価値あるものなのではないでしょうか。